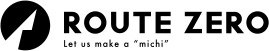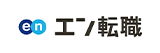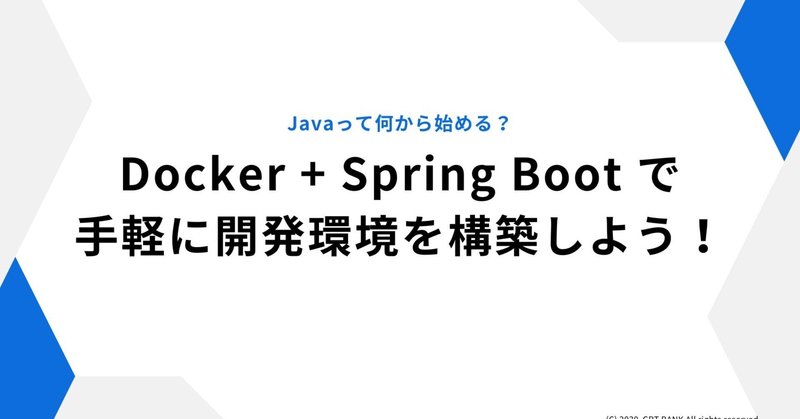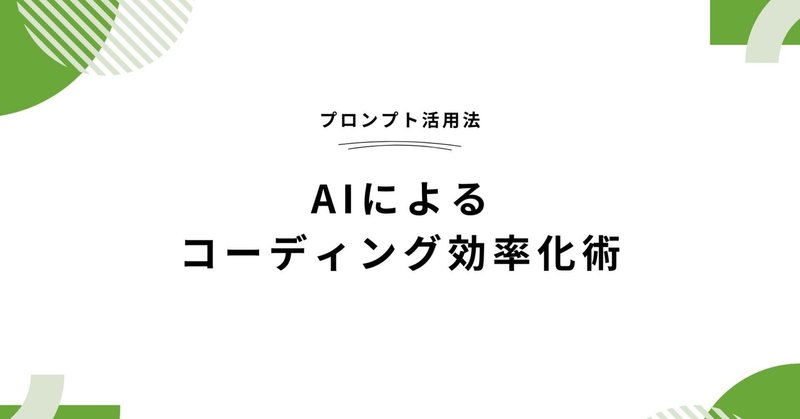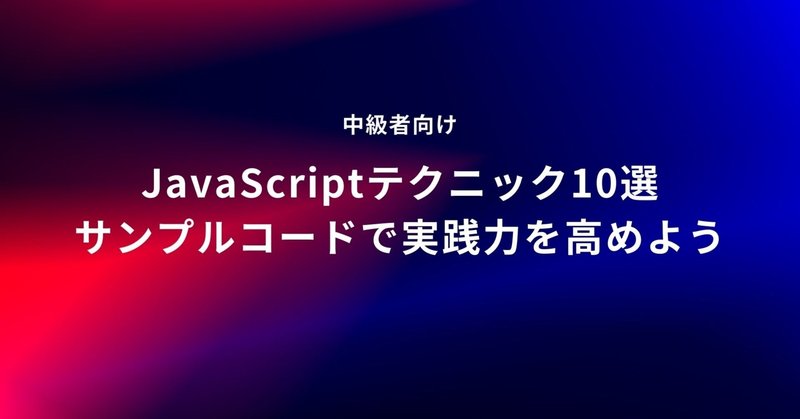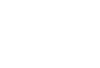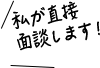ウォーターフォール型とは?工程の順番と流れを図で見るシステム開発の基本
「ウォーターフォール」という言葉、よく耳にしますよね。
でも――「どんな工程で進むの?」「どこから関わればいいの?」と聞かれると、説明に詰まる人も多いはずです。
私たちが現場で使うウォーターフォールモデルは、いまもシステム開発の王道。
この記事では、図と表で“全体の流れ”をつかみながら理解できるように整理してみました。
焦らず順番に追えば、開発プロセスの全景が見えてくるはずです。
モヤモヤを一緒に解消しましょう。
1. ウォーターフォールモデルとは?
滝のように「上から下へ流れる」――それがウォーターフォールモデルの語源です。
各工程を一つずつ確実に終わらせてから次へ進む計画的な開発スタイルです。
用語解説:ウォーターフォールモデル
システム開発の進め方の一つ。工程を順番に進め、前の工程が終わってから次へ進む「滝の流れ」のようなスタイル。計画性が高く、文書化や進捗管理がしやすいのが特徴です。
-
順序性が高い:要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → 運用
-
手戻りが少ない:前の工程を確定してから次へ進む
-
文書化がしっかり:設計書・仕様書を詳細に残す
アジャイル開発が「柔軟さ」を売りにしているのに対し、
ウォーターフォールは「計画性」と「再現性」が武器です。
「最初に全部決めてから作る」――これが最大の特徴です。
2. 全体フローを図で理解しよう
開発の流れは6つのフェーズで構成されます。
| フェーズ | 目的 | 主な成果物 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 何を作るか決める | 要件定義書、仕様書 |
| 基本設計 | 全体構造を設計 | 基本設計書 |
| 詳細設計 | プログラム設計 | 詳細設計書 |
| 実装 | コードを書く | ソースコード |
| テスト | 動作を検証する | テスト仕様書、報告書 |
| 運用・保守 | リリース後の改善 | 運用マニュアル |
📊 フロー図イメージ
要件定義 → 基本設計 → 詳細設計 → 実装 → テスト → 運用・保守
(上流工程)———————————(下流工程)
成果物を確定させながら次に進むため、進捗管理しやすいのが利点。
一方で、途中変更には弱い構造でもあります。
3. 各工程の役割を具体的に見てみよう
🔹 要件定義
「何を作るか」を明確にする最初のステップ。
顧客と開発チームのゴールをそろえる段階です。
用語解説:要件定義
システムで「何を実現したいか」を明確にする工程。顧客の要望や目的を整理し、必要な機能や条件を文書にまとめます。
🔹 基本設計
システムの構造やデータの流れを決めます。
画面構成図やシステム構成図がここで生まれます。
用語解説:基本設計
システム全体の構造や動き方を設計する工程。画面や機能の配置、データの流れなどを図や文書で整理します。
🔹 詳細設計
プログラム単位での設計を詰める工程。
このあたりからSESエンジニアが本格参加することも多いです。
(SESエンジニアのキャリアや参画方法については『未経験からSESエンジニアへ!現場参画でキャリアを築く方法』もご参照ください)
用語解説:詳細設計
プログラムや機能ごとに、具体的な処理内容や手順を設計する工程。どんなコードを書くか、細かく決めます。
🔹 実装
設計書に沿ってソースコードを書く段階。
レビューや単体テストもここで行います。
用語解説:実装
設計書をもとに、実際にプログラム(ソースコード)を書く工程。動作確認やレビューも含まれます。
🔹 テスト
不具合を検出し、品質を保証します。
単体 → 結合 → 総合 → 受入と段階的に進めるのが定番。
用語解説:テスト
作成したシステムやプログラムが正しく動くかを確認する工程。単体テスト(部品ごと)、結合テスト(組み合わせ)、総合テスト(全体)、受入テスト(顧客確認)などがあります。
🔹 運用・保守
リリース後のサポートフェーズ。
ユーザーの声を次の改善につなげていきます。
用語解説:運用・保守
システムを公開した後、安定して使えるように管理・改善する工程。トラブル対応や機能追加も含まれます。
4. SESエンジニアが関わる主な工程
SESエンジニアが参画するのは主に詳細設計〜テスト工程ですが、
上流工程(要件定義・基本設計)を担当することもあります。
一般的には発注側や元請けが担うことが多いですが、
実務的な領域だけでなく幅広く関わるケースも増えています。
用語解説:SESエンジニア
SES(システムエンジニアリングサービス)契約で、顧客先に常駐し技術支援を行うエンジニア。設計や実装、テストなど幅広い工程に関わります。
| フェーズ | 主な役割 |
|---|---|
| 詳細設計 | モジュール設計・レビュー補助 |
| 実装 | コーディング・単体テスト |
| テスト | 結合テスト・品質確認 |
まずは設計書の読み解き方を身につけることが第一歩。
その理解が、上流工程へのキャリアアップにもつながります。
5. メリットとデメリットを整理しよう
✅ メリット
-
工程と責任範囲が明確
-
設計書が充実しており品質を担保しやすい
-
大規模・官公庁系など安定した開発に最適
⚠️ デメリット
-
途中の変更が難しい
-
要件の不備が後半で発覚すると修正コストが高い
-
実際の動作を確認できるのが遅い
そこで現場では、各フェーズの終わりにレビューゲートを設けて
「この時点で問題ないか」を確認しながら進めます。
6. アジャイルとの違いもざっくり把握
| 項目 | ウォーターフォール | アジャイル |
|---|---|---|
| 進め方 | 上流→下流の一方向 | 小単位で反復 |
| 柔軟性 | 低い | 高い |
| 文書量 | 多い | 必要最小限 |
| 向く案件 | 長期・安定型 | 変化が多い短期型 |
(アジャイル開発の実践やテスト設計については『Spring Bootテスト設計入門:TDD×モック×CI自動化ガイド』も参考になります)
用語解説:アジャイル開発
小さな単位で開発・テストを繰り返し、柔軟に仕様変更に対応できる開発手法。スピード重視で、変化の多いプロジェクトに向いています。
ウォーターフォールは「完成度重視」、
アジャイルは「スピード重視」。
プロジェクトの性格で選び分けるのが現実的です。
7. まとめ:全体像を理解すれば迷わない
ウォーターフォール開発は、システム開発の基本を学ぶのに最適なモデルです。
流れを理解しておくと、SESエンジニアとして自分がどこに立っているかを明確にできます。
「上流から下流までの見取り図」を頭に描けるようになると、
現場の会話やレビューでも発言の幅が広がります。
まずは自分の関わる工程を整理し、
次はアジャイルやハイブリッド開発に視野を広げてみましょう。
ぜひ手元のプロジェクト図を見返しながら、工程の流れを追体験してみてください。
カジュアル面談のご案内
「評価制度ってどんな仕組み?」「スキルと単価の関係ってどうなってる?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひエントリーしてみてください。
制度の詳細や案件選びのポイントについて、カジュアルにお話しできます。
エントリーはこちらから。