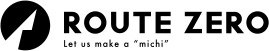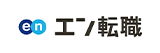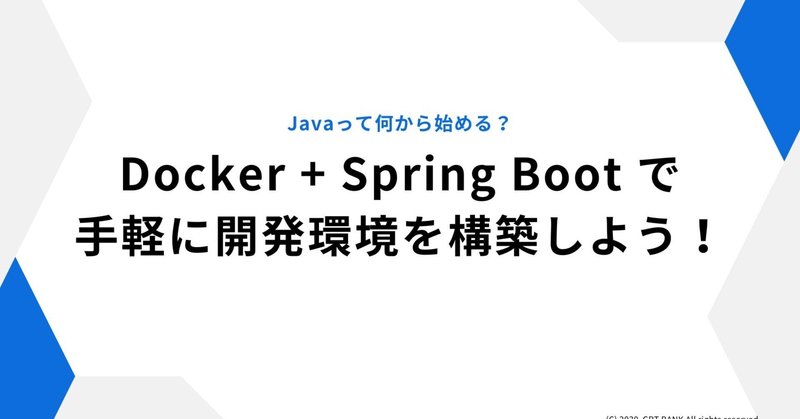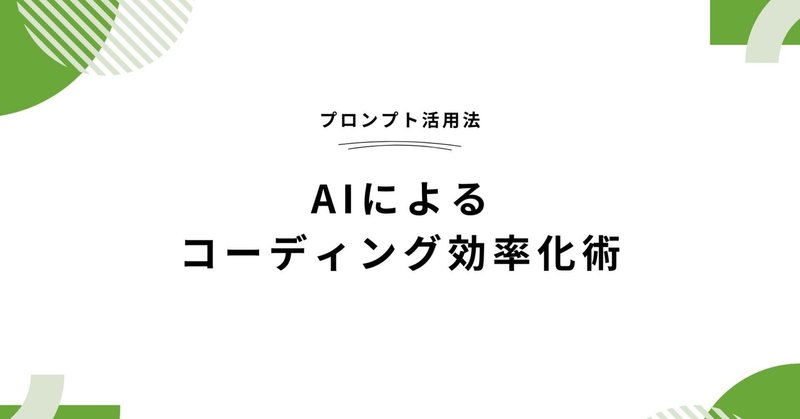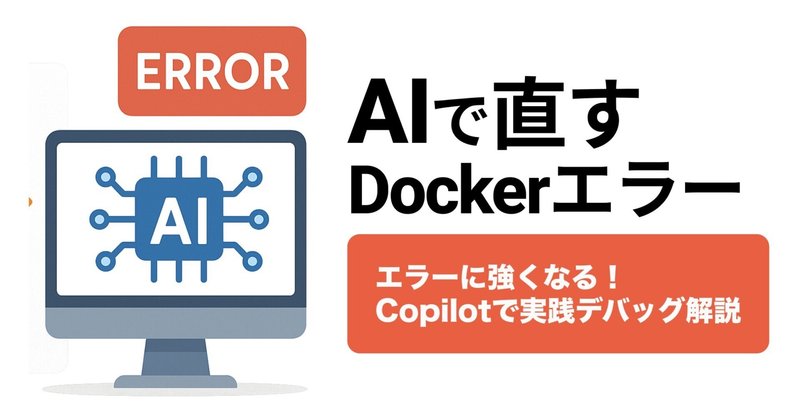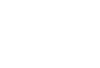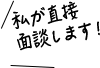はじめに
「SESエンジニアを目指したいけど、何から始めればいいのか分からない」
「SESで働いているけど、この先どう動けばいいのか不安」
こう感じて検索している方は少なくありません。
SESは“エンジニアとしての入口”になりやすい一方で、キャリア停滞や案件選びの不透明さに悩む声もあります。本記事では、SESエンジニアとしてキャリアを始める際に押さえるべき基礎知識・スキル・働き方の注意点を整理します。
SESエンジニアとは?まず知っておきたい仕組み
SESの働き方と契約構造
SES(システムエンジニアリングサービス)は、エンジニアが自社ではなくクライアント企業に常駐して業務を行う働き方です。多くは準委任契約で、成果物ではなく「業務時間」に対して報酬が支払われます。
用語解説:SES(システムエンジニアリングサービス)
クライアントに技術者を常駐させ、時間単位で技術支援を行う契約形態。成果物の納品を前提とするのではなく、業務遂行そのものを提供します。用語解説:準委任契約
「結果(完成)」ではなく一定の業務を誠実に遂行する義務を負う契約。作業範囲や時間単価を契約書で取り決めるのが一般的です。
受託・自社開発との違い
-
受託開発:自社で請け負い、完成物を納品
-
自社開発:自社サービスを自社内で開発
-
SES:クライアント現場に常駐し、開発や運用に携わる
用語解説:受託開発/自社開発/SES
受託=成果物納品型、自社開発=自社プロダクト型、SES=時間提供型。
同じ「開発」でも契約責任や評価軸が異なるため、キャリア設計上の前提が変わります。
SESは経験を積みやすい一方で、「自社にノウハウを蓄積しにくい」という特徴もあります。
SESエンジニアは何から始めるべきか
押さえておきたい基礎スキル
SES案件で特に多いのは業務系システム開発です。そのため、JavaやSQLは最初に習得しておくべきスキルといえます。(Javaの学習手順については『SES エンジニアのための Java 学習ロードマップ完全版』をご参照ください)
-
Java:大規模な業務システムや金融系システムで長く使われており、保守・運用案件も豊富。初学者でも学習リソースが多く、案件参画後の実務で役立ちやすい。
-
SQL:システム開発では必ずといっていいほどデータベース操作が伴います。SQLの理解があると、バグ調査やレポート作成など日常業務に直結します。(SQLスキルの重要性については『SESエンジニア必見!SQLスキルの必要性と単価相場』をご参照ください)
用語解説:業務系システム
受発注、会計、人事など、企業の業務処理を支えるシステム群。信頼性・保守性を重視するため、Java+RDB(SQL)の比重が高くなります。用語解説:Java/SQL
Java=大規模・長期運用に強い言語。
SQL=データベースに対する問い合わせ言語。検索(SELECT)、登録(INSERT)、更新(UPDATE)、削除(DELETE)を扱います。
加えて、設計書を理解できる読解力や、Webアプリケーションの基本構造を把握しておくと現場でのキャッチアップがスムーズになります。
用語解説:設計書
画面・機能・データの仕様を図や文章でまとめた「開発の設計図」。基本設計/詳細設計などの粒度があります。用語解説:Webアプリケーションの基本構造
ブラウザ(フロントエンド)⇄サーバ(バックエンド)⇄データベースの三層構造が基本。HTTPやAPIの理解が土台になります。
社内で評価されやすいスキル
技術スキルに加えて、報連相(報告・連絡・相談)やコミュニケーション力が評価に直結します。常駐先の文化に馴染める柔軟性も重要で、トラブル時に冷静に対応できる力は信頼を得る上で欠かせません。
用語解説:報連相(ホウレンソウ)
進捗・課題・判断材料をタイムリーに共有する行動様式。常駐先との信頼関係やリスク低減に直結します。
案件経験をどうキャリアに変えるか
ただ業務をこなすだけではスキルが定着しません。
-
参画した案件の技術スタックを記録する
-
学んだことを記事や勉強会でアウトプットする
-
定期的にスキルシートを更新する(スキルシートの具体的な書き方については『SESスキルシートの書き方完全ガイド』をご参照ください)
このように経験を可視化しておくと、次の案件や転職活動に活かしやすくなります。
用語解説:技術スタック
プロジェクトで用いる言語・フレームワーク・DB・ツールの組み合わせ。用語解説:スキルシート
参画案件・役割・使用技術・実績を一覧化した職務経歴ドキュメント。配属や評価の材料になります。
SESでキャリアを積むメリットとデメリット
メリット:案件の幅・経験の積みやすさ
-
多様な現場を経験できる
-
未経験からでも参入しやすい
-
大規模システムに関わる機会が多い
デメリット:スキル停滞リスク・単価非公開問題
-
配属内容によってはテストや保守に偏りやすい
-
単価や評価基準が不透明だと、自分の市場価値を把握しづらい
停滞を打破するには?
保守やテスト中心の案件に長く留まると、開発スキルが身につかないまま年数だけが経ってしまうこともあります。これを防ぐには、
-
スキルアップを目的とした案件希望を定期的に伝える
-
社内評価面談で「次に挑戦したい技術領域」を明確にする
-
個人学習で不足スキルを補い、実務にアサインされやすい状態を作る
といった積極的な動きが求められます。受け身でいるとキャリアは停滞しやすいため、主体的に働きかける姿勢が重要です。
向いている人・向いていない人
-
向いている人:柔軟性があり、現場に合わせて成長していける人
-
向いていない人:同じサービスや技術を長期的に深掘りしたい人
キャリアを広げるためのステップ
案件選びで意識すべきポイント
-
使用する技術が自分のキャリア軸と合っているか
-
長期的にスキルアップにつながるか
-
会社が案件の情報をどこまで開示しているか
単価・評価制度を理解する重要性
SESでは「自分が顧客に請求されている単価」と「給与」が必ずしも一致しません。単価や評価制度がどのように設定されているかを理解しておくことが、納得感を持って働くために大切です。
用語解説:単価
1人月(または時間)あたりの請求金額。スキル・役割・難易度で変動します。用語解説:評価制度
成果・スキル・態度などを評価する社内ルール。昇給・配属・教育方針に影響します。透明性が高いほど納得感が得られます。
まとめ:SESエンジニアが最初にやるべきこと
学習・案件・制度理解の3つを押さえる
-
学習:JavaやSQLなど基礎スキルを固める
-
案件:キャリアにつながる案件を選ぶ視点を持つ
-
制度理解:単価や評価制度の仕組みを理解しておく
情報収集と相談を並行する
求人票や噂だけでは判断できない点も多いため、同業の先輩や転職エージェントに相談するのも一つの手です。さらに、SES企業のカジュアル面談で実際の仕組みを直接聞くのも有効です。現場経験や制度の透明性について具体的な話を聞くことで、自分の価値観と合う働き方を選びやすくなります。
FAQ
Q1. SESエンジニアは未経験でもなれる?
→ はい。多くのSES企業では研修制度や基礎教育を用意しているため、未経験からの参入も可能です。ただし学習の姿勢が求められます。
Q2. 不透明な案件配属を避けるには?
→ 事前に「案件選定の仕組み」や「単価の透明性」について確認しておくことが有効です。
Q3. SESで経験を積んだ後のキャリアパスは?
→ 自社開発企業への転職や、より専門的な分野へのキャリアチェンジなど複数の選択肢があります。
カジュアル面談のご案内
「評価制度ってどんな仕組み?」「スキルと単価の関係ってどうなってる?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひエントリーしてみてください。
制度の詳細や案件選びのポイントについて、カジュアルにお話しできます。
エントリーはこちらから。