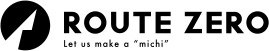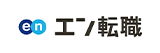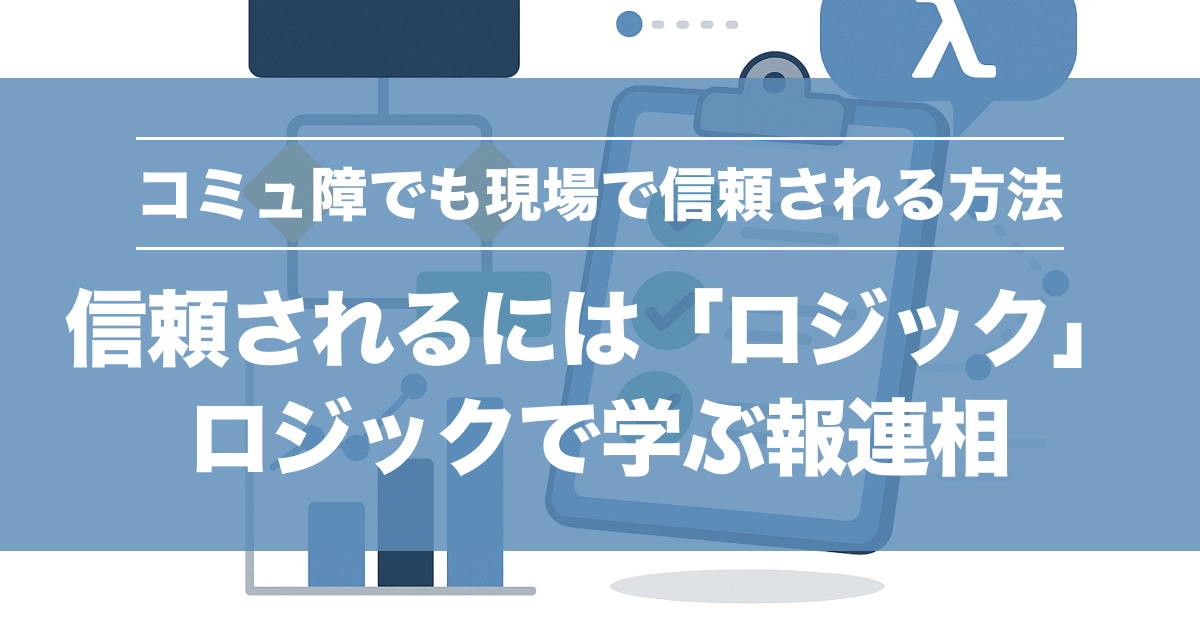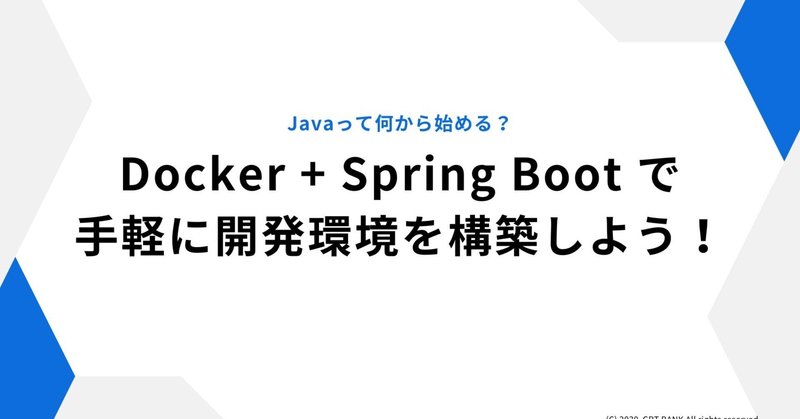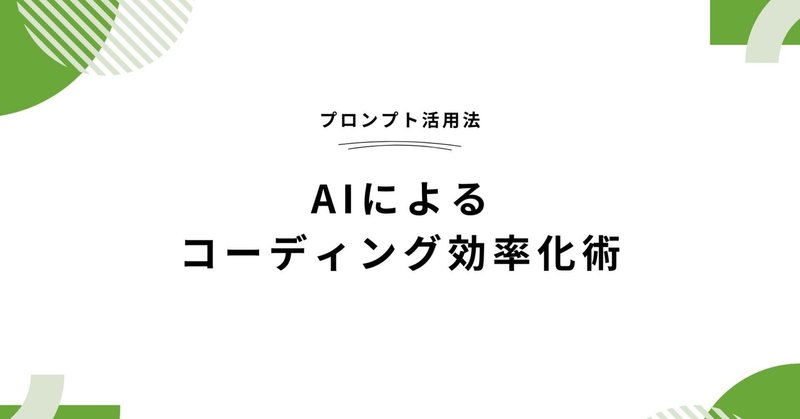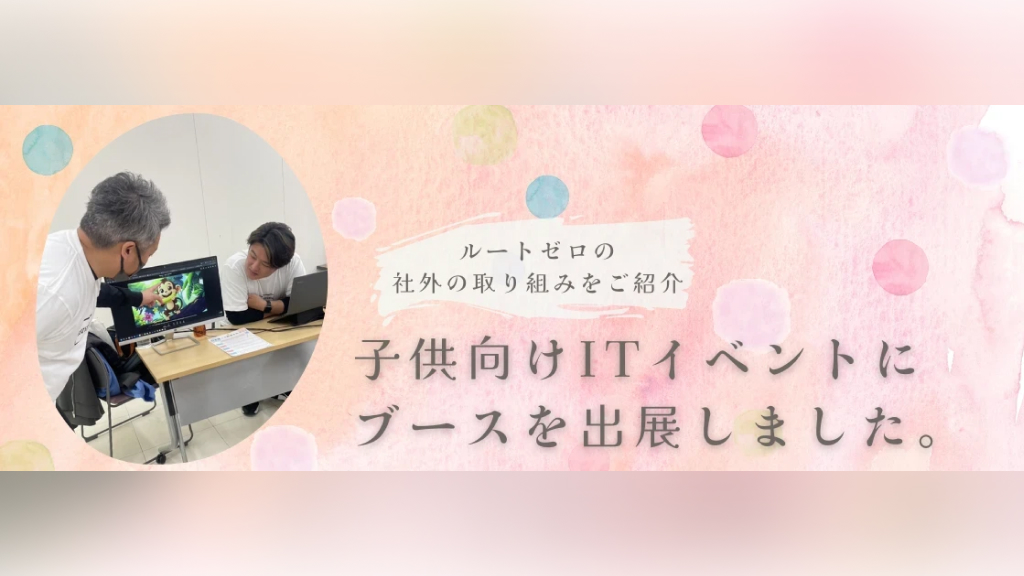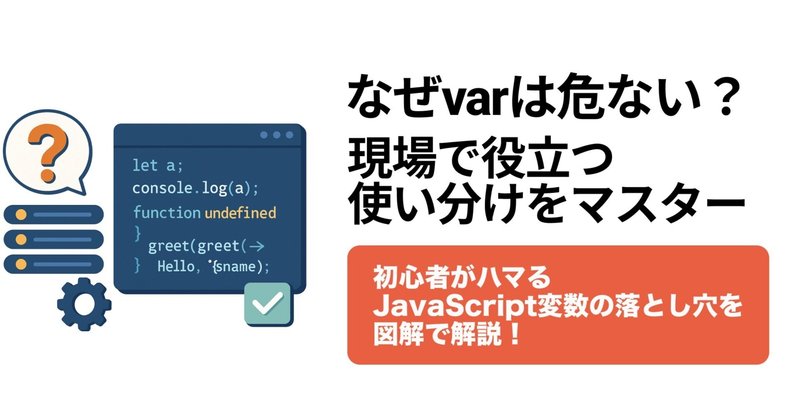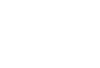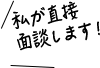【SESエンジニア必見】現場で信頼されるコミュニケーションは「ロジック」で学べる
「技術力には自信があるのに、なぜか現場で評価されない…」「報連相はしてるはずなのに、いつもすれ違いが起きる…」。SESエンジニアとして働くあなたは、そんな漠然とした悩みを抱えていませんか?
「コミュニケーション術」と聞くと、雑談力や愛想の良さが重要だと思われがちですが、それは大きな誤解です。真に評価されるコミュニケーションは、感覚ではなく「仕組み」や「ロジック」で習得できるものだからです。
この記事では、SESで働くエンジニアの「コミュニケーション」に特化し、今日から実践できる具体的なテクニックを解説します。現場での信頼獲得はもちろん、あなたの市場価値を上げ、最終的に「配属先が運任せではない」納得のいくキャリアへと繋がる道筋を、ロジックと数字で徹底的に解き明かします。
(SESエンジニアの業務全体像については『SESエンジニアとは?4ステップで業務フロー&スキル完全ガイド』をご参照ください)
SESエンジニアが抱えるコミュニケーションの「本当」の課題
多くのエンジニアにとって、コミュニケーションは「得意な人だけが持っている特殊能力」のように感じられるかもしれません。しかし、それは違います。技術スキルと同様に、コミュニケーションもまた論理的に分解し、一つずつ身につけていくことができます。
用語解説:SES(システムエンジニアリングサービス)
クライアント企業に技術者を常駐させ、専門技術やノウハウを時間単位で提供するサービス形態。準委任契約で結ぶため、業務範囲を契約書で細かく定義できます。
「コミュニケーション=雑談」ではないという誤解
あなたが悩んでいるのは、決して「雑談が苦手」という表面的な問題だけではありません。SESエンジニアの場合、以下のような構造的な課題が潜んでいます。
-
技術情報以外のコミュニケーション不足: 案件に常駐していると、会社のメンバーとの交流が希薄になり、技術以外のキャリアや評価に関する情報に触れる機会が減ります。
-
現場での役割が不明瞭: 顧客のプロジェクトにアサインされるため、「チームの一員」としてどう振る舞うべきか、迷うことがあります。
-
「報連相」の目的を見失っている: 「報告しなければならない」という義務感だけで行動し、その報告が「相手にどう役立つか」という視点が抜けてしまうことがあります。
これらはすべて、ロジックで解決できる課題です。技術力があるにも関わらず、これらの課題に直面し、正当な評価を得られていないと感じているのは、あなたの責任ではありません。必要なのは、論理的にコミュニケーションを捉え直すことです。
ロジックで学ぶ、SESエンジニア向けコミュニケーション術
ここからは、感覚に頼らず、今日から実践できるSES業界で活躍するためのコミュニケーション術を、具体的な「型」としてご紹介します。
【報連相】単なる報告ではなく「相手を動かす」報連相のフレームワーク
報連相は、単に事実を伝える行為ではありません。それは、相手に「適切な行動」を促すためのトリガー(引き金)です。このフレームワークを意識しましょう。
-
結論から話す: 何か問題が起きたら、まず「〜の不具合が発生しました」と結論を伝えます。
-
現状と事実を簡潔に: 「原因はまだ特定できていませんが、〇〇というログが出ています」など、客観的な事実のみを伝えます。
-
次に取るべき行動を提案: 最も重要です。「これから調査を続けますが、先にAさんにも状況を共有しておいた方がいいでしょうか?」のように、相手が次に取るべき行動を具体的に提案します。
この流れで報連相を行うことで、相手は「次に何をすればいいか」を瞬時に理解でき、あなたは「自分で考えて行動できる人」と評価されるようになります。
(報連相の実践や現場での注意点については『SES現場の品質担保完全ガイド|失敗しない方法・条件分岐のポイントも解説』をご参照ください)
用語解説:報連相(ホウレンソウ)
「報告・連絡・相談」の略。業務の進捗や課題を上司やチームに適切に伝えるための基本的なビジネススキル。
【質 問】「何を、なぜ、誰に」を明確にする3ステップ質問法
質問が苦手な人は、「相手に迷惑をかけていないか?」と過度に気にする傾向があります。しかし、適切な質問は信頼を築くツールです。
-
「何を」聞きたいか: 質問の本質を明確にする。「〇〇の仕様で、〜の挙動について教えていただきたいです」
-
「なぜ」聞きたいか: 質問の背景を共有する。「〜という機能の実装にあたり、認識を合わせるためです」
-
「誰に」聞くか: 質問の相手を特定する。「Aさんにお伺いしてもよろしいでしょうか?」
この3ステップを意識するだけで、相手はあなたの質問意図を素早く理解し、建設的な会話が生まれます。
【議事録】面倒な議事録が「信頼」に変わる書き方テンプレート
議事録は、単なるメモではありません。それは「会議で決まったこと」を記録し、チーム全体の認識のズレを防ぐための重要なドキュメントです。
-
項目を固定: 決定事項、TODO、課題・懸念事項、次回MTG日時
-
人名を明記: 「〇〇(タスク名)はAさんが担当」のように、誰が何をするのかを明確にする。
-
決定事項に「なぜ」を添える: 「今回は〇〇の理由でA案を採用」と、意思決定の背景を明記することで、後から見返した時の解像度が格段に上がります。
このテンプレートに従えば、あなたの議事録は「ただの文字の羅列」ではなく、チームの生産性を高めるための重要なツールへと変わります。
用語解説:議事録
会議や打ち合わせで決まった内容や課題、担当者などを記録した文書。後から内容を確認したり、認識のズレを防ぐために活用されます。
【関係構築】雑談が苦手でもOK!現場で「信用」を積み重ねる小さな習慣
用語解説:コミュニケーション能力
相手の意図を正しく理解し、自分の考えや状況を分かりやすく伝える力。ビジネス現場では信頼関係の構築やチームワークに直結します。
雑談が苦手でも心配いりません。以下の習慣を実践することで、あなたは技術とは別の観点から信用を積み重ねることができます。
-
期日を守る: 些細なタスクでも、期日通りに完了させることで「この人に任せておけば大丈夫」という信頼感が生まれます。
-
チャットのレスポンスを早くする: 「確認しました」の一言でも良いので、返信を素早く返すことで、相手に安心感を与えます。
-
感謝の気持ちを伝える: 「〜さんのおかげでスムーズに進みました、ありがとうございます!」と、こまめに感謝を伝えることで、相手はあなたと働くことにポジティブな感情を抱きます。
FAQ:SESエンジニアのコミュニケーション、よくある質問
-
Q1. SESの現場で「コミュ障」だと不利ですか?
不利になることはありません。技術力と同じくコミュニケーションも学習・改善が可能です。この記事で紹介したような「ロジック」で捉えれば、あなたの強みである技術力と同じ思考で攻略できます。
-
Q2. 報連相のタイミングがわからず、いつも怒られてしまいます。
報連相は「遅すぎる」より「早すぎる」方が良いと考えるべきです。不明点や進捗の遅れは、小さなうちに報告することで大きなトラブルを防げます。
-
Q3. 技術力とコミュニケーション、結局どちらが重要ですか?
どちらも重要ですが、キャリア初期は「技術力」が、中堅以降は「コミュニケーション能力」がより重要になる傾向があります。技術力がベースとなり、その上でコミュニケーション能力があなたの市場価値を最大化します。
-
Q4. 現場で仲の良い人がいません。孤立していても大丈夫ですか?
必ずしも仲良くなる必要はありません。重要なのは、円滑に業務を遂行できる「信頼関係」を築くことです。仕事上のコミュニケーションがスムーズであれば、孤立していると感じることは減っていくはずです。
まとめ
この記事では、SES業界で活躍するためのコミュニケーション術を、「ロジック」という観点から解説しました。
-
コミュニケーションは感覚ではなく、「報連相」「質問」「議事録」といった具体的な「型」で習得できる。
-
信頼を積み重ねる小さな習慣が、非技術的なスキルとしてあなたの市場価値を高める。
-
コミュニケーション能力の向上は、給与や評価に繋がり、納得感のあるキャリアを築くための重要な要素である。
「このままでいいのか?」というあなたの漠然とした不安は、コミュニケーションを論理的に捉え、スキルとして磨くことで解消できます。そして、そのスキルを正当に評価してくれる企業と出会うことが、次のキャリアを考える上で最も重要です。
(SESエンジニアのキャリアアップやスキル戦略については『SESポートフォリオ完全ガイド|5年後も選ばれるエンジニアのキャリア戦略と作り方』をご参照ください)
カジュアル面談のご案内
「評価制度ってどんな仕組み?」「スキルと単価の関係ってどうなってる?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひエントリーしてみてください。
制度の詳細や案件選びのポイントについて、カジュアルにお話しできます。
エントリーはこちらから。