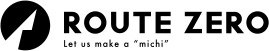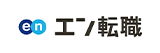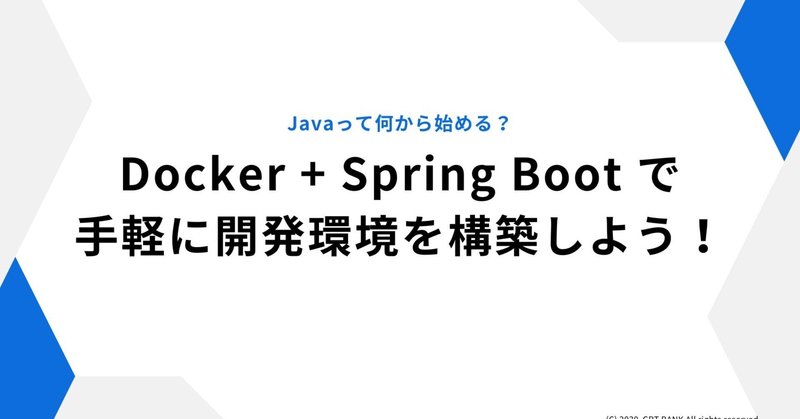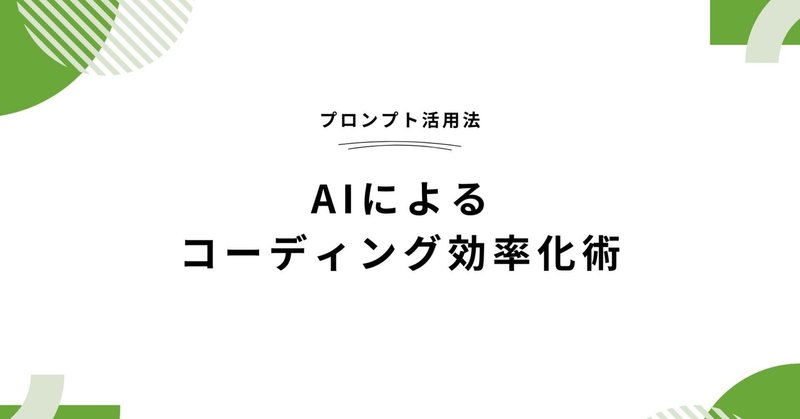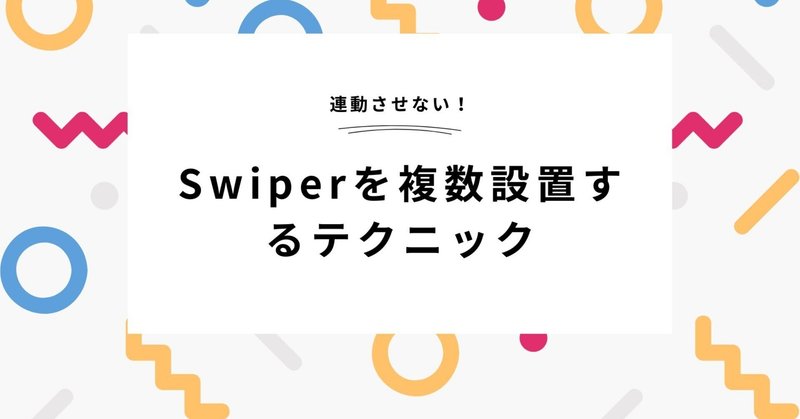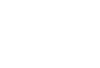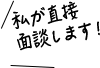はじめに|ノーコード・ローコードの“モヤモヤ”を言語化しよう
「ノーコード」「ローコード」の違い、現場やSNSでよく耳にするけど、いざ説明しようとすると曖昧で困ることありませんか?
IT系エンジニアの間でも「両方知っておきたいけど、本質的な違いが言語化できない」「“知ってて良かった”と言いたい」と感じる方が多いはず。
本記事では現場目線でノーコード/ローコードの定義・違い・使い分け・メリット・デメリットを徹底整理。
・自信を持って違いを説明したい
・現場でどう選び、使い分ければいいか知りたい
そんな方に向けて、“エンジニア仲間のナレッジ”をまとめました。
1. ノーコードとローコードの違い:考え方・定義から見直そう
■ ノーコードは「コードを書かない」開発スタイル
ノーコードは、プログラミング知識が不要で、画面操作やパーツのドラッグ&ドロップだけでシステムやアプリを作れる方式です。
例:業務アプリ・簡単なウェブサービス・フォーム作成など、短期間で試したい場面に向いています。
コーディングの心理的ハードルを大きく下げてくれるのが特徴です。
(ノーコード・ローコードの現場活用事例については『汎用統合エージェントでAI仕様書・プロンプト設計は本当に使える?【事例解説】』もご参照ください)
用語解説:ノーコード
プログラミング(コード記述)を一切せず、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)上の操作だけでアプリやシステムを作成できる開発手法。専門知識がなくても利用できるのが特徴。用語解説:ドラッグ&ドロップ
マウス操作でパーツや要素を移動・配置する直感的な操作方法。ノーコードツールでよく使われる。用語解説:GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)
画面上のボタンやアイコンなど、視覚的に操作できる仕組み。コマンド入力不要で直感的に使える。
■ ローコードは「少しコードを書く」柔軟な開発
ローコードは、ビジュアル操作が中心ですが、最低限のコードで細かい要件やカスタマイズも可能な開発方法です。
例:標準機能だけでは足りない業務ロジックやシステム連携を、自分で“少し書いて”補うイメージ。
「ゼロから全部書く」よりも効率的に、「ノーコードじゃ無理」な部分もカバーできます。
用語解説:ローコード
画面操作を中心にしつつ、一部だけコード(プログラム)を記述して柔軟なカスタマイズや拡張ができる開発手法。ノーコードよりも自由度が高い。用語解説:業務ロジック
システムやアプリが現場の業務ルールに従って動作するための処理や仕組み。用語解説:システム連携
複数のシステムやサービスをつなぎ、データや機能をやり取りできるようにすること。
■ どちらも“開発の敷居”を下げる仲間
ノーコードもローコードも、「誰でも開発に関われる世界」を広げる技術。
目的や状況に応じて“最適な使い分け”が現場の鍵です。
(現場での開発手法や働き方の違いについては『SES・SIer・自社開発の違い徹底比較!あなたに最適な働き方は?』もご参照ください)
用語解説:開発の敷居
システムやアプリ開発に必要な知識・スキル・コストなどの「参入障壁」のこと。ノーコード/ローコードはこの敷居を下げる。
2. ノーコードとローコード、どう使い分ける?“現場基準”の整理
■ ノーコードが向いているケース
- 要件がシンプル
- すぐ試したい・コストや期間が限られている
- プログラミング知識がない現場メンバーが自作したい
例:社内向け申請フォームや業務効率化の小ツールなど。
「自分で手を動かしてみたい」現場に選ばれる傾向があります。
用語解説:要件
システムやアプリに「何が必要か」「どんな機能がいるか」をまとめたもの。
■ ローコードを選ぶべき場面
- 標準機能だけでは足りない複雑な業務
- システム連携や細かいカスタマイズが必要
- 拡張や将来のアップデートも見据えたい
「最初はノーコードでプロトタイプ、後からローコードで拡張」する流れも一般的です。
「業務要件の複雑さ」「手持ちスキル」「将来の発展性」を基準に選択しましょう。
用語解説:プロトタイプ
本格開発の前に、動作や使い勝手を試すために作る「試作品」や「たたき台」。用語解説:カスタマイズ
標準機能に加えて、独自の機能やデザインを追加・変更すること。用語解説:拡張性
システムやアプリが将来的に機能追加や変更に柔軟に対応できる度合い。
3. SESエンジニアの“リアル”——現場で感じる迷いと整理法
■ こんなとき、どう判断する?
- ノーコードでOKと言われたが、途中で「この部分だけ独自処理が必要」と気づいた
- ローコードの案件、どこまで自動化して、どこから手書きするのが最適?
現場エンジニアもこうした「迷いどころ」によく直面します。
用語解説:独自処理
標準機能では対応できない、特定の業務や要件に合わせて個別に作るプログラムや処理。用語解説:自動化
人手を介さず、システムが自動で処理を行う仕組み。
■ ナレッジとして整理するコツ
- 「どの要件でどちらが最適だったか」迷った経験もメモ
- 使ったツールごとの“得意/不得意”も記録
- “ハマった”ポイントや判断の分岐点をナレッジ化
まずは身近なプロジェクトで「使い分け」を自分で試してみるのがおすすめです。
用語解説:ナレッジ
経験や知識、ノウハウをまとめて共有・活用できる形にしたもの。用語解説:分岐点
どちらの方法を選ぶか判断が分かれる重要なタイミングや条件。
4. ノーコード/ローコードのメリット・デメリット
■ ノーコードの良さと弱み
メリット:
- 非エンジニアでも“作る”体験ができる
- 短期間&少人数でスタートしやすい
- 運用・保守も比較的ラク
デメリット:
- 複雑な業務や独自要件には不向き
- ツール依存度が高い
- 拡張・柔軟性は制限されやすい
用語解説:ツール依存
特定のサービスやツールに頼りきりになること。他のツールへの移行や機能追加が難しくなる場合がある。用語解説:運用・保守
システムやアプリを継続的に使い続けるための管理・メンテナンス作業。
■ ローコードのメリットと注意点
メリット:
- 一部コードでカスタマイズや連携が柔軟
- 拡張性や将来の発展も考えやすい
デメリット:
- コーディング知識は最低限必要
- 設計次第で開発が複雑化しやすい
用語解説:コーディング
プログラムのコード(命令文)を書く作業。用語解説:設計
システムやアプリの構造・動作・仕様を事前に決めること。設計が複雑だと開発も難しくなる。
どちらも万能ではないからこそ、「どんな場面でどちらを選ぶか」が現場の腕の見せ所です。
(ノーコード・ローコードの選び方や失敗例については『フリーランスとSES企業の違い徹底比較|制度・働き方・選び方』もご参照ください)
5. よくある疑問Q&A——現場の“モヤモヤ”を解決
-
Q. ノーコードだとエンジニアは不要になる?
A. いいえ。ノーコードは非エンジニアでも活用できますが、要件整理やシステム連携など技術者の知見が不可欠な場面は必ず残ります。
むしろ現場では、エンジニアがツール選定や運用設計をサポートするケースが増えています。 -
Q. ローコードでエンジニアの仕事は減る?
A. 手作業や“ゼロからの開発”は減っても、「ツール選定」「要件の切り分け」「設計力」など新しいスキルが必要になります。仕事が減るというより、役割や価値の形が変化すると考えましょう。 -
Q. 結局どっちを覚えるべき?
A. どちらか一方に偏るより、どんな場面でどちらを使うか判断する力がこれからの現場で重宝されます。知識として両方を押さえておくことで、プロジェクト対応の幅が広がります。
用語解説:要件整理
システムやアプリに必要な機能や条件を明確にまとめる作業。用語解説:運用設計
システムをどのように使い、管理・保守していくかを計画すること。用語解説:スキル
業務や開発に必要な知識や技術力。用語解説:役割
チームやプロジェクト内で担当する仕事や責任範囲。
まとめ——自分なりの“使い分け基準”を持とう
ノーコードもローコードも「開発のハードルを下げ、誰もがアイデアを形にしやすくする」ための技術です。
どちらが“正解”というより、現場の目的や要件、使う人のスキルによって最適解が変わります。
迷ったら、まずは小さく試してみて、経験をナレッジとしてストックしましょう。
あなたの現場での判断材料に、この記事が少しでも役立てばうれしいです。